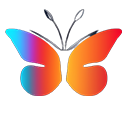ピナ・バウシュ略歴

目次
バイオグラフィー - ダンスとその劇場の構成
1940年7月27日、ドイツ・ラインラント州ゾーリンゲン生まれ。 1973年以来、ドイツ・ヴッパタールを拠点とする世界的な振付機関「ピナ・バウシュ・ヴッパタール舞踊劇場」を主宰。 舞踊史における最も重要な振付家のひとり。正確には「シアター・ダンス」というのだろうが、これはバウシュ自身の意向を文字どおり翻訳したものであり、彼女自身の考えを確信犯的に支持したものであった。当時、バウシュは、いわゆるバレエに縛られ、ギャグにとらわれ、ジェスチャーや表現に注意を払い、それを際立たせることなく、振付の概念を壊していた。ダンスの表現力、ひいては演劇性に。
彼女の作品における音楽と音楽的インスピレーションの重要性を強調するために、彼女自身の作品の定義はしばしば「ダンス・コンポーザー」である。
しかし、バウシュの始まりは非常に厳しく、困難なものだった。 実際、思春期前の小さなピナは、ダンスを夢見ることしかできなかった。 父親が経営する小さなレストランで働き、あらゆることを少しずつこなし、時々、運悪く、町の惨めな劇場でオペレッタに小さな役で出演することもあった。 しかし、最初はダンスクラスもダンスレッスンもない、それどころか、12歳ですでに41サイズの靴を履いているのだから。
15歳の1955年頃、彼女はエッセンの「フォルクヴァング・ホッホシューレ」に入学した。この学校は、偉大なルドルフ・フォン・ラバンによって創始されたアウスドラックシュタンツの美学的潮流、いわゆる表現主義舞踊の弟子であり推進者であったクルト・ヨースの指導によるものであった。 4年後の1959年、若いダンサーは卒業し、「ドイツ・アカデミッシャー・アウスタウシュディエンスト」から奨学金を受けた。未来の「ダンス・シアター」の創造者に、アメリカでの上級トレーニングと交流コースを提供する。
関連項目: アンドレア・マイナルディ略歴ピナ・バウシュは、ニューヨークのジュリアード音楽院で「特待生」として学び、アントニー・テューダー、ホセ・リモン、ルイス・ホルスト、ポール・テイラーらとともに研鑽を積んだ。 すぐに、1957年に設立されたポール・サナサルド&ドーニャ・フォイヤー舞踊団に入団。 アメリカでは幸運が舞い込み、何よりもヨーロッパよりも彼女の優れた才能に目を留めてもらえた。 彼女は、ニュー・アメリカン・バレエ団と、そのバレエ団で執筆契約を結んだ。メトロポリタン・オペラ・バレエは、チューダー自身の指揮のもとで行われた。
関連項目: ルチアーノ・リガブー伝1962年、巨匠クルト・ヨースに誘われてドイツに戻り、再建されたフォルクヴァング・バレエ団のソロ・ダンサーを務めることになった。 しかし、アメリカは遠く、バウシュは帰国後に見たドイツの現実に失望した。 そんな彼女に唯一ついていけそうだったのが、1967年と1969年の2回、イタリアでスポレート・フェスティバルを共に踊った、クルト・ヨースだった。ダンサー、ジャン・セブロンは数年来のパートナーだった。
1968年、フォルクヴァング・バレエ団の振付師となり、翌年、フォルクヴァング・バレエ団の監督を務めると同時に、自身の作品の創作を開始。 1969年の「Im Wind der Zeit」で、ケルンの振付作曲コンクールで1位を獲得。 1973年、ヴッパタール・バレエ団の監督に招かれ、まもなく「ヴッパタール・タンツ劇場」と改名。この冒険には、バウシュのほか、舞台装置のロルフ・ボルツィク、ダンサーのドミニク・メルシー、イアン・ミナリック、マルー・アイラウドが参加している。
彼女のショーは当初から大成功を収め、演劇はもちろんのこと、文学や芸術の最も重要な名作からインスピレーションを得た作品として、あらゆる場所で高い評価を得た。 1974年、このドイツ人振付家は、マーラーとフフシュミットの音楽を使った「フリッツ」を創作し、翌年にはグルックの「オルフェウスとエウリュディケ」、そして非常に重要な作品であったストラヴィンスキーの三連作「Frühlingsopfer」は、「西からの風」、「Der zweite Frühling」、「Le sacre du printemps」から成る。
ピナ・バウシュの芸術作品における真の転機となった傑作は「カフェ・ミュラー」である。 この作品には、父親が経営するレストランで若い労働者として働いていた彼女の過去のエコーも感じられる。 ヘンリー・パーセルの音楽に合わせて、振付家自身を含む6人のパフォーマーが踊る40分間の作品である。 この作品には、動詞、言葉、そして作品全体の発見がある。笑ったり泣いたりするような、強く純粋で、情景が目に浮かぶような、インパクトのある感情を表す音や、悲鳴、突然のささやき声、咳払い、うめき声など、より大きく、時には破裂するような音など、さまざまなオリジナルの音がある。
ピナ・バウシュの新表現主義は、1980年の「アイン・シュトゥック・フォン・ピナ・バウシュ」でも、より鮮明に見ることができる。 ダンサーである彼女の姿は、日常的な服装で舞台を動き、経験し、日常的なことでさえする、一人の人間へと「変身」している。ある種の批評家たちからの非難は強く、ピナ・バウシュもまた、特にアメリカの批評家たちから、下品で趣味が悪いと非難されている。 彼女の革新的な作品にはリアリズムが多すぎるという声もある。
ピナ・バウシュはこの時期、いくつかの映画にも参加している。盲目の女性を演じたフェデリコ・フェリーニ監督の『E la nave va』や、1989年の長編映画『Die Klage der Kaiserin』などである。
当初、オランダ人セット・衣装デザイナーのロルフ・ボルツィックと結婚したが、1980年に白血病で死去。
ローマとパレルモで大成功を収めた後、1991年にはマドリッドで「タンザベンドII」を上演し、ウィーン、ロサンゼルス、香港、リスボンでも成功を収めた。
1990年代の終わりには、1996年のカリフォルニアの「Nur Du」、1997年の中国の「Der Fensterputzer」、1998年のポルトガルの「Masurca Fogo」など、軽めの、しかし重要なカットを持つ3つの作品が日の目を見た。
文字通り世界中を旅した晩年の10年間では、2001年の「アグア」、2003年の「ネフェス」、2006年の「ヴォルモンド」が特筆に値する。 一方、2008年の「ドルチェ・マンボ」は、彼の最後の作品であり、注目に値する。
2009年、彼女はヴィム・ヴェンダース監督による挑戦的な3D映画プロジェクトに着手したが、振付家自身の急死により中断。 2009年6月30日、ピナ・バウシュは癌のためヴッパータールで死去、享年68歳。
2011年に公開されたドキュメンタリー映画『ピナ』は、すべて彼女のダンス・シアターに捧げられたもので、第61回ベルリン映画祭で公式上映された。